まさに AI 全盛の時代である。
どのニュースを見ても AI、AI、AI。
気づけば「人間より賢い」「人間を超える」といった言葉が並び、話題はもっぱら知能の話ばかりになっている。
ところが不思議なことに、この「知の大合唱」のただなかで、正反対とも言えそうな言葉が目立つようになってきた。それが「感情」「情動」「感性」である。
考えてみれば、人間は昔から「知・情・意」でできているとされてきた。「知」だけを磨けばよい、という話には、そもそもなっていなかったはずだ。「知」が前に出れば出るほど、「情」が気になってくる。これはどうやら、人間の性(さが)らしい。
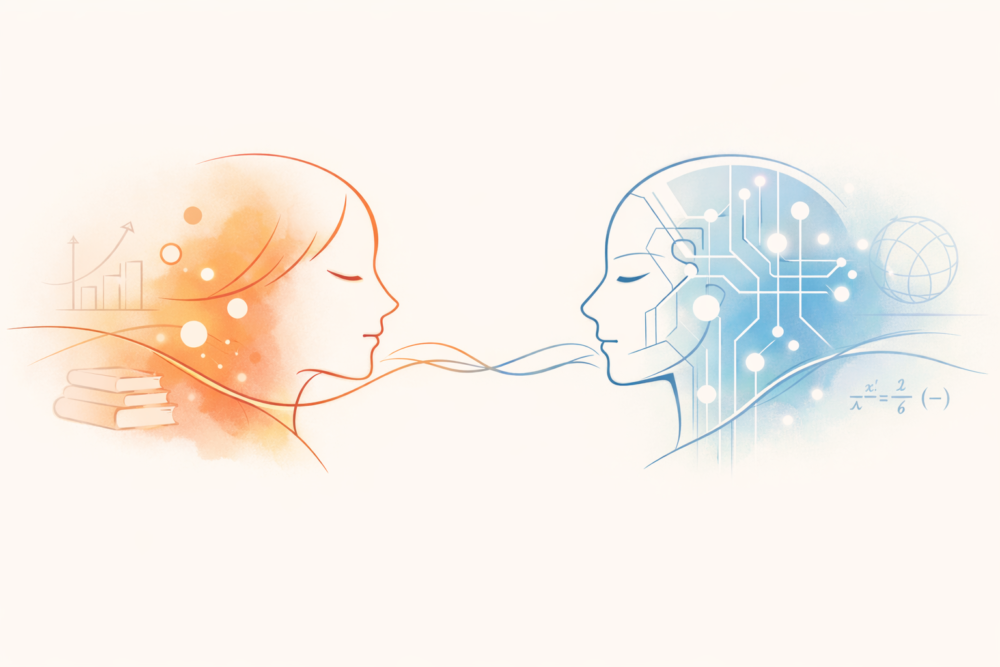
身体・感情・知性はつながっている
2025年の大阪・関西万博(EXPO2025)は、まさに技術の祭典だった。いわば「知」のお祭りである。ところがその会場では、意外なほど多く、「感情」「ウェルビーイング」「メンタルヘルス」をテーマにしたイベントが開かれていた。心身医学に関係するカンファレンス「Unlocking the Mind-Body Connection(こころとからだの関係を解く)」でも、失感情症と身体の関係について、なかなか熱のこもった議論が交わされていた。
感情は身体と深く結びついているが、もちろん知性とも無縁ではない。脳科学の研究からも、知性・感情・身体は別々に働いているのではなく、常に影響し合いながら機能していることがわかってきている。それらは、互いに連絡を取り合う独立した要素というよりも、連続したスペクトラムのようなものなのだ。
「わかっちゃいるけど、やめられない」
植木等の『スーダラ節』は、じつに人間の本質を突いている。「わかっている」のは知性であり、「やめられない」のは情動である。ここでは情動が少し困った存在として描かれているが、そもそも感情抜きで行われる知的活動など、現実の世界ではほとんどありえない。
私たちは自分のことを「よく考えてから行動する生きもの」だと思っている。しかし実際には、その順番はしばしば逆である。
危険を感じて思わず身を引く「とっさの反応」はもちろん、昼ごはんに何を選ぶか、朝どの服を着るかといった日常的な選択も、まず直感が決まり、理屈はあとから追いかけてくる。「これを選んだ理由」は、後づけの説明であることが少なくない。
こうした行動は、そのときの身体の状態にとって「いちばんしっくりくる反応」として起きているとも言える。身体があり、感情が動き、そのうえで知性が語りだす。すでに述べたように、身体―感情―知性は、切れ目のない一本の線でつながっている。
AI 時代にあらためて問われる「人間らしさ」
ここで思い出されるのが、夏目漱石『草枕』の有名な一節である。
「草枕」夏目漱石
智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。
とかくに人の世は住みにくい。
知・情・意のどれか一つだけで生きようとすると、どうも無理が生じるらしい。
人間社会が面倒なのは、この三者のバランスを取り続けなければならないからなのだろう。そういえば、忘年会や新年会といった「情の交流」も、近年あらためて見直されつつあると聞く。
AI、すなわち「人工知能」がこれほど注目される時代に、あらためて「感情」や「情動」が話題になるのも、決して偶然ではない。
2026年の年頭、メディアは相変わらずAI一色だが、その一方で、「こころとからだはどう結びついているのか」、さらには「人間らしさとは何か」といった問いが、静かに、しかし確実に浮かび上がってきている。
人間とは何者なのか。
そして、私たちはどんな存在としてAIと向き合うのか。
そんなことを、少し立ち止まって考えてみる年のはじまりにしたい。
(Kanbara K, Psychosomatic Labo/ LABs Psychosomatic Medicine, https://psychosom.net/ai-human, Jan. 2026)
